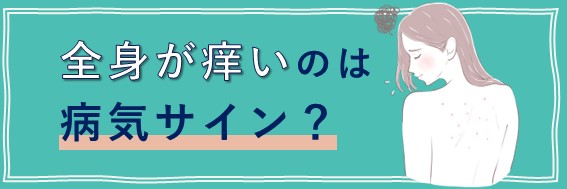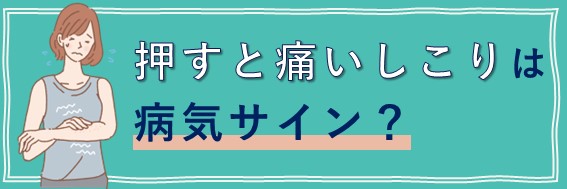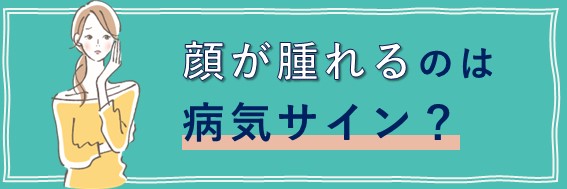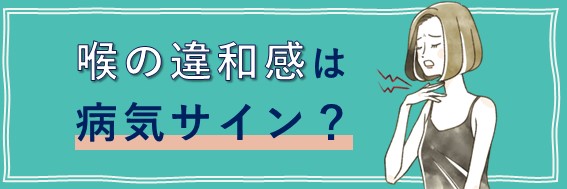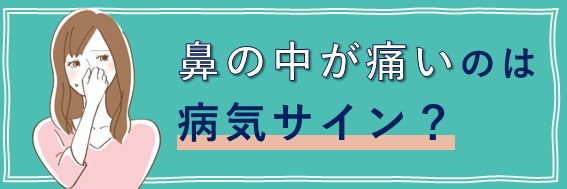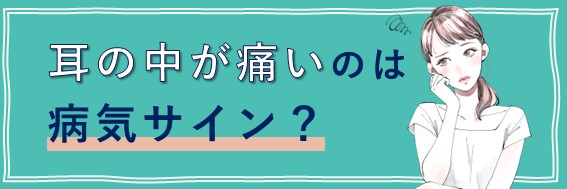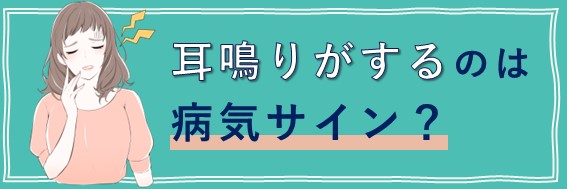おたふく風邪は、冬から初夏ごろまでが感染が多い時期です。
大人にうつると重症化しやすい傾向があります。
「どういう感染ルートからうつるのか」「いつからいつまで感染するのか」をお医者さんに聞いてみました!
監修者
平塚共済病院 小田原銀座クリニック 久野銀座クリニック
内科医
岡村 信良先生
経歴
平塚共済病院 小田原銀座クリニック 久野銀座クリニック
おたふく風邪の「感染経路・期間」


おたふく風邪の感染ルートは「飛沫感染」と「接触感染」の2つです。
- 飛沫感染の例…ウイルスが入った咳を吸い込む
- 接触感染の例…ウイルスが付着した手が体に触れる
人にうつしてしまう期間は、耳下腺の腫れがでる数日前~腫れが引くまでです。
おたふく風邪の病原体はムンプスウイルス(mumps virus)です。このウイルスの潜伏期間は2~3週間。「おたふく風邪だ」と気がつく前から、ウイルスを排出しています。
▼おたふく風邪の経過(目安)
|
|
症状
|
日数目安
|
|
潜伏期間
|
なし
|
2~3週間程度
|
|
発症
|
耳の周り・あごの下・舌の周りなどに腫れ、高熱
女性:下腹部痛、吐き気、不正出血
男性:急激な精巣の痛み・腫れ・発熱・倦怠感
|
1~2週間程度
(発熱は2〜3日程度、痛みのピークは腫れが出てから数日間)
|
|
回復
|
上記症状が少しずつ改善される
|
おたふく風邪の「予防方法は?」

おたふく風邪の原因のムンプスウイルスは感染力がとても高いです。免疫がない人は容易に感染します。そのためおたふく風邪から子どもを守れるのは、現在予防接種だけです。
また、おたふく風邪が流行る時期はマスクの着用・手洗い・うがいを行わせましょう。
家族が感染したら…どうすれば?

もし家族のうちの誰かが感染してしまったら、他の人はマスクの着用・手洗い・うがいを徹底して予防に努めてください。
ただし、上述の通り、ムンプスウイルスの感染力は非常に強く、完璧に予防することは困難です。
これまで、おたふく風邪にかかっていないのであれば、予防接種を受けることが最善といわれる予防策です。過去に一度おたふく風邪にかかっている場合は、免疫ができているので、基本的には再びかかることはありません。
もし感染してしまった場合は、消化に良いものを食べ、自宅で安静に過ごしましょう。
予防接種が大切です
基本的には、子どもが1歳を過ぎたら、予防接種を受けさせましょう。予防接種を受ければ、万が一発症しても軽い症状で済みます。
1回の予防接種では免疫がつかない場合があるので、2回接種を行ってください。日本では任意予防接種ですが、1歳以上であれば予防接種を受けられます。費用目安は5000円前後であることが多いです。(医療機関や為替の変動によっても異なります。)
おたふく風邪の予防接種はなぜ任意なの?
ワクチン接種後の無菌性髄膜炎等の問題があり、1993年に定期接種は中止されました。
ワクチンの副反応はあるものの、重篤な副反応の頻度は0.1%未満ですので、安全性は高いと考えて良いでしょう。
「子ども」は軽症で済むことが多いけど…

おたふく風邪は、3~6歳の子どもに多いです。
予後は良好で対症療法で快方に向かうことが多いです。
しかし、症状があきらかな患者のうち10%程度が髄膜炎を発症すると推定されているため、油断は禁物です。その他にも脳炎・難聴などの合併症も一定数あります。
「大人」が感染すると、重症化しやすい

おたふく風邪は、大人にもうつります。
成人が感染すると症状が重くなる傾向があります。
女性の場合は卵巣炎・男性の場合は精巣炎を合併することもあります。すぐに回復した場合は問題ないこともありますが、悪化すると不妊につながることがあるので、注意が必要です。
▼卵巣炎の症状
下腹部痛・吐き気・不正出血など
→すぐに婦人科を受診してください。
▼精巣炎の症状
精巣の痛みや腫れ・発熱・倦怠感など
→すぐに泌尿器科を受診してください。
特に、妊婦さんは要注意!
また、妊娠早期で感染すると流産することもありますから、大人になってからの感染は注意が必要です。
ただし「基本的に2度はかからない」

何度もおたふく風邪にかかるといった人がいますが、おたふく風邪は1度かかると免疫ができるので、通常は2度はかかりません。
※稀に、免疫ができないと、再びかかる人もいます。
おたふく風邪の免疫ができているかどうかは、検査すればわかります。
おたふく風邪の免疫があるかどうか自分ではわからないという方は、医療機関で血液検査をして、抗体があるかを検査しましょう。
2度かかったと思ったら「反復性耳下腺炎」かも
おたふく風邪と間違いやすい症状が出る病気に「反復性耳下線炎」があります。おたふく風邪にかかったことがある/予防接種をしたのにおたふく風邪のような症状が出ている場合、この病気であることが多いです。
▼「反復性耳下腺炎」の症状の特徴
- 片側だけが腫れやすい
- 熱はでない場合が多い
- 痛みは軽く、数日で完治するが、何度も繰り返しかかる
※反復性耳下腺炎は、人から人にはうつりません。
おたふく風邪がうつってしまったときの対処法

自宅で安静に過ごしてください。お食事は消化の良いものを食べましょう。口を開けるのがつらい期間は、流動食がおすすめです。
スープ、プリン、ゼリー、お粥、うどんなどが良いでしょう。ただし、酸っぱい食べものは、唾液腺を刺激して痛みが出るので、避けてください。
学校・仕事にいってもいいのはいつから?

登園・登校・出社できるのは、腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になってからとなっています。
このころには、熱も下がり、食欲も出ているはずです。それまでは安静に過ごしましょう。
おたふく風邪の「特に注意すべき症状」

危険な合併症を引き起こしている可能性がある症状として
- 頭痛が強い
- 嘔吐する、嘔吐を繰り返す
- 意識障害
- 高熱が3〜4日以上続く
- 耳下腺の腫れが1週間以上治らない、赤く腫れている
などが挙げられます。
合併症として難聴・内耳炎・髄膜炎・睾丸炎・乳腺炎などを引き起こしている場合があります。特に難聴は治らない場合もあります。
これらの症状がある場合は、夜間でも救急で受診しましょう。
小児科を探す
合わせて読みたい

2022-02-18
おたふく風邪は、ムンプスウイルスの感染症です。
お医者さんに、「大人のおたふく風邪(流行性耳下腺炎)」について聞きました。
大人が発症すると重症化し、女性でも男性でも不妊の原因になることも。
おたふく風邪の「初期症状」や、「仕事に行ってもいい基準」を解説してもらいました。
大人にもおたふく風邪はうつる?
おたふく風邪は、大人もかかるんですか?
重症化しやすいと聞きましたが…。
はい。おたふく風邪は大人になって発症すると症状が重くなる傾向があります。症状の経過は同じですが、大人の方が体内に入ったウイルスに抵抗する力が強いため、その反動で症状が強く出てしまう傾向にあります。
また、大人がかかりやすく、重症化しやすい合併症として卵巣炎や精巣炎があります。
原因となるムンプスウイルスは感染力が高いので、免疫がなければ容易に大人にうつります。
おたふく風邪の感染ルート
おたふく風邪の感染ルートは飛沫感染(くしゃみ等)や接触感染(ウイルスがついた手で触れる等)です。
予防には、マスクの着用・うがい・手洗いも有効ではありますが、ムンプスウイルスは感染力がとても強いウイルスなので、積極的な予防には、予防接種(2回接種)が有効です。
予防接種を受ければ、万が一発症しても軽い症状で済みます。
合わせて読みたい
おたふく風邪はどううつる?感染経路や期間、予防法も|医師監修
2019-07-29
おたふく風邪は、冬から初夏ごろまでが感染が多い時期です。大人にうつると重症化しやすい傾向があります。「どういう感染ルートからうつる...
続きを読む
ただし「一度かかっていればかからない」
1度感染したことがあるのですが、2回おたふく風邪にかかることもありますか?
一度おたふく風邪にかかっていれば、免疫ができています。
基本的には、2度はかかりません。
子どもの時におたふく風邪になっていれば、うつらないはずです。
※稀に免疫ができていない場合があります。免疫があるかは、検査でわかります。
おたふく風邪の免疫があるかを調べる方法
おたふくかぜの原因である「ムンプスウイルス」の抗体価を血液検査で調べます。IgMとIgGという2種類ムンプスウイルスの抗体価を調べることでわかります。
検査は、内科や耳鼻科、小児科などの医療機関で受けられます。
疾患が疑われて検査する場合は、保険適用となりますが、それ以外の通常の検査であれば自費(保険適用外)で4000〜7000円程度かかります。
大人のおたふく風邪の初期症状
ウイルスの潜伏期間は、2~3週間です。
初期症状には、
耳下腺の違和感
飲食時・酸っぱいものを飲んだときの耳下腺の痛み
などがあります。
おたふく風邪を発症すると、耳の周り・あごの下・舌の周りなどに腫れが生じます。高熱がでる人も多くいます。発熱は2〜3日程度、痛みのピークは腫れが出てから数日間となるでしょう。
※症状には個人差があり、熱がさほどでない場合や腫れが弱い人もいます。また、感染しても症状が現れない(不顕性感染)人も多く、30〜35%程度あるとされています。
合併症・後遺症の例
合併症
合併症のリスク
合併症がでる確率
髄膜炎
軽症であり、後遺症なく治癒することが多い。
10%
難聴
永続的な聴覚障害となる。
0.1~0.25%
脳炎
命を落とす。
0.02~0.3%
膵炎
軽症か無症状であり、約 1 週間の経過で軽快する。
10% 以下
精巣炎
不妊につながる。
20~30%
卵巣炎
不妊につながる。
7%
女性の合併症
女性がおたふく風邪にかかると、まれに「卵巣炎」を合併症で発症します。
下腹部痛、吐き気、不正出血などを伴います。
「卵巣炎」とは、病原体が子宮経管から卵管に感染して炎症が起きる病気です。不妊症につながる恐れがあるため、該当症状がある場合は、すぐに婦人科を受診しましょう。
妊婦さんは特に注意!
妊娠早期で感染した場合、流産の危険性もあります。
免疫があるか検査した上で、免疫がない女性が妊娠を望んでいる場合は、予防接種を受けましょう。妊娠中におたふく風邪かもと思ったら、かかりつけ医を受診し、体調管理の指示や薬の処方を受けましょう。
男性の合併症
精巣に炎症が起きる病気「精巣炎」を発症する場合があります。
現れる症状は、急激な精巣の痛み・腫れ・発熱・倦怠感などです。
すぐに回復した場合、不妊の原因となることは稀です。
しかし悪化させると不妊症の原因となる場合があります。
大人がおたふく風邪にかかってしまったら…
もしおたふく風邪にかかってしまったら、どうすればいいでしょうか…?
自宅で安静に過ごし、お食事は消化の良いものを食べてください。
おすすめの食事
口を開けるのがつらい期間は、流動食がおすすめです。
スープ、プリン、ゼリー、お粥、うどんがよいでしょう。
ただし、酸っぱいものは、唾液腺を刺激して痛みが出るので、避けてください。
仕事はいつから行ける?
仕事にいけるのはいつからですか?
おたふく風邪のウイルスは、非常に感染力が強いです。
厚生労働省による感染症対策ガイドラインによると、出社できるのは、「腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になってから」とされています。
それまでは、感染を拡大させる恐れがあるので、腫れがある時期は自宅で休養が望ましいです。
腫れが引いていれば、ウイルス排出は終わっているので、出社してもよいでしょう。念のため、マスクを着用し、手洗いを行いましょう。
大人のおたふく風邪「病院は何科?」
男性か女性かによって受診する診療科が違います。
男性:泌尿器科を受診
女性:婦人科を受診
妊婦:かかりつけの産婦人科に連絡して指示を仰ぐ
泌尿器科を探す
婦人科を探す
合わせて読みたい
片方の耳の下が痛い!腫れるけど熱はなし「反復性耳下腺炎」かも。病院は何科?
2020-06-25
子どもが「片方の耳の下が痛い」と訴える。腫れているけど、熱はないみたい…これは何?もしかして「反復性耳下腺炎」もしくは「おたふく風...
続きを読む
▼参考
おたふくかぜワクチンの接種対象者・接種方法及びワクチン - 厚生労働省
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) - 厚生労働省
流行性耳下腺炎(ムンプス、おたふくかぜ) - 国立感染症研究所
合わせて読みたい

2020-03-24
「なんだか最近風邪をひきやすくなった…」
こんな風に感じている方も多いのではないでしょうか?
風邪をひきやすくなるのは、疲労など生活習慣の乱れをはじめ、隠れた病気の可能性もあるので、注意が必要です。
体質を改善して、風邪をひきにくくする方法もご紹介します。
風邪をひきやすい原因
風邪をひきやすい人の特徴
睡眠不足
睡眠時間が短い場合、免疫グロブリン(IgA)※の分泌量が低下しやすくなると考えられています。
※免疫グロブリン(IgA)
血液中や組織液中に存在している免疫に関わる物質
激しい運動をしている
運動強度が強いほど、免疫グロブリン(IgA)が低下するため、免疫力も低下すると考えられています。
不規則な生活習慣
生活習慣が乱れると、自律神経やホルモン分泌の制御を行っている体内時計も乱れてしまい、免疫力が低下しやすくなると考えられています。
ストレスが溜まっている
過度のストレスを抱えている場合、自律神経のバランスが崩れて、免疫グロブリン(IgA)の分泌が低下して免疫力が弱くなる場合があります。
栄養が偏っている
骨や筋肉等、体の組織を構成しているタンパク質、細胞やホルモンを生成する元となる脂質等と一緒にバランスの良い食べ物を摂るようにしてください。
ドライマウス
口腔内が乾燥し、粘膜も乾燥していると、免疫グロブリン(IgA)の働きが鈍くなり、ウイルスや細菌が侵入しやすくなるため、風邪をひきやすくなります。
冷え性
体温が低下すると免疫力も低下するので、風邪をひきやすくなります。
痩せすぎ
体温維持、身体にビタミンを運ぶ、女性ホルモン調節等の役割を担っている脂肪が少ないと、風邪をひきやすくなります。
腸内細菌のバランスが悪い
腸内細菌のバランスが悪いと、便秘を起こしやすくなる、免疫力が低下する等になり、風邪をひきやすくなると考えられています。
糖質制限をしている
人が生きていくために必要とされているエネルギー源の約半分を糖質が占めています。
その糖質を必要以上に制限すると、身体のエネルギー量が減少します。
すると、体力維持が困難になり、風邪をひきやすくなる等が起こると考えられています。
加齢で免疫細胞が減少している
加齢に伴い、正常に機能してくれる免疫細胞が減少する、新たに生成された免疫細胞の機能も低い等により、免疫力が低下して、風邪をはじめとする感染症を起こしやすくなります。
女性特有の原因
ホルモンの影響
生理前になるとプロゲステロンの分泌が多くなります。
この期間は、免疫力が低下しやすいため、風邪をひきやすくなると考えられています。
妊婦中
妊娠中は、次の理由で免疫力が低下しやすい状態です。
ホルモンバランスが不安定になりやすい
つわりがある場合は食事を十分摂取できず栄養不足になりやすい
ストレスを溜めやすい
睡眠不足になりやすい 等
また、お腹にいる胎児を異物として捉えないように、NK細胞やマクロファージ等の細胞性免疫が相対的に減ると考えられています。
産後
産後は、女性ホルモンが減少し、ホルモンバランスが崩れやすくなります。
また、赤ちゃんのお世話に追われ、睡眠不足、疲労、ストレス過多状態になりステロイドホルモン※の分泌が多くなる場合があります。
その結果、免疫力が低下し風邪をひきやすくなります。
※ステロイドホルモン
炎症や免疫を抑制する働きがあるホルモン
赤ちゃんは風邪をひきやすい?
赤ちゃんは、母乳を通してママから免疫をもらっています。(IgA等)
しかし、その免疫が有効に作用する期間は6か月程度と考えられており、それ以降は自力でウイルスや細菌から自分自身を守らなければなりません。
自分を守る免疫力は、いろいろな病原体等に曝されて少しずつ獲得できるものなので、乳幼児はまさに免疫を得る過程にあることで風邪等の感染症を発症しやすいと考えられています。
風邪をひきやすい体質は改善できる?
次のことを実践して、体質改善に努めましょう。
喉の潤いを維持する(水分をこまめに摂る)
加湿する(加湿器、マスク等)
体を温める(湯船に浸かる等)
適度に運動する(ストレッチ、ヨガ、ウォーキング等)
良質な睡眠を十分とる(抗体を作るリンパ球の働きは睡眠時に活発になる)
手洗い、うがいを徹底する
栄養バランスの良い食事を摂る
体質改善におすすめの食べ物
次の栄養素を積極的に摂りましょう。
ビタミンB1
豚肉、マグロ、レバー、ゴマ、ほうれん草、卵、海苔等
ビタミンE
イワシ、サバ(青魚)、たらこ、かぼちゃ等
上記に加え、生姜、にんにく、ねぎもおすすめです。
風邪をひきやすくなる病気
免疫不全症候群
先天的原因と後天的原因(HIVウイルスによるエイズ)に分けられています。
細菌やウイルス等に対する抵抗力や免疫力がないことで、感染症を繰り返しやすくなる状態です。
糖尿病
血糖値が高いため、白血球や免疫細胞の働きが弱まり病原体等と闘うことができない状態になり、感染症に罹りやすいと考えられています。
自律神経失調症
自律神経のバランスが崩れると体温調節が困難になり、身体が衰弱して風邪等を起こしやすくなると考えられています。
肝臓疾患、腎臓疾患(亜鉛吸収障害)
肝臓疾患や腎臓疾患等を発症すると亜鉛不足(亜鉛吸収障害)を起こす場合があります。
亜鉛が不足すると、免疫力が低下して風邪をひきやすくなると考えられています。
白血病
正常な白血球が減少することで、風邪(感染症)に罹りやすくなると考えられています。
癌や恒常性疾患
癌や甲状腺疾患の治療で、二次的に風邪をひきやすくなる場合があります。
治療に用いられる薬によって免疫が下がり、風邪をひきやすくなります。
こんな症状があれば病院へ
次のような症状が現れたら、医療機関を受診しましょう。
2週間以上せきが続く場合
咳をすると胸に痛みが生じる場合
血痰がでる場合
高熱(38度以上)が3日以上続く場合
一回症状が回復しても、数日後にまた体調が悪化した場合
体がガタガタ震えて止まらない場合(悪寒戦慄)
上記以外にも、普段と何か違うと感じる場合は、早めに医療機関(内科)を受診してください。
内科を探す
(参考URL)
http://www.nagasaki.med.or.jp/mini_info/index.htm#a_01
長崎県医師会 かぜ対策
https://www.nagahama.jrc.or.jp/care/medical-checkup/himan-yase
日本赤十字社 長浜赤十字病院 肥満と病気、やせと病気
https://www.mcfh.or.jp/netsoudan/article.php?id=1468
公益財団法人 母子衛生研究会 病気・予防接種
http://www.kracie.co.jp/ph/k-kampo/hikihajime_no_hikihajime/results3.html
クラシエ こんなときは早めの対処を!知っておきたいかぜのサイン
https://www.otsuka.co.jp/b240/mechanism/reason2.html
大塚製薬 免疫力低下の原因
http://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/070/070/01.html
糖尿病情報センター 糖尿病と感染症のはなし
https://www.mcfh.or.jp/netsoudan/article.php?id=317
公益財団法人母子衛生研究会 病気・予防接種
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO3942922027122018000000/?page=3
日本経済新聞電子版 一見「風邪」だが実はちがう 受診すべき6つの症状